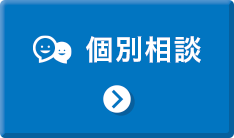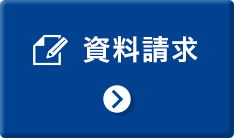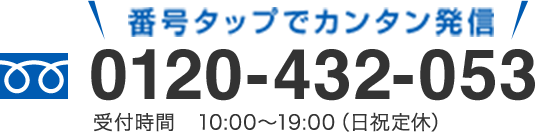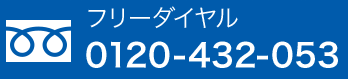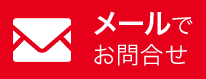そもそも勉強においてのモチベーションに関してですが、あくまでモチベーションというのは勉強をしている状態のときにどれだけの調子を出せるかというのが大きいです。
勉強のやる、やらないというのは好き嫌いに近いものです。
その上で勉強が嫌い、やる気がない子のよく言いがちなセリフとその原因に対処するために塾で行っていることについてお伝えします。 ・「考える気持ちを持続できない」
これはとりあえず問題を解くなどのアウトプットに偏った勉強をしている子が陥りやすいです。 私ももアウトプットに偏っているときは集中が途切れたり、進みが遅くなったりしました。 しかし勉強の中でも学校の授業を聞く、用語の暗記をする、復習をするなどの行為はインプットが多い勉強なので問題集とのバランスを考えた勉強になるようにしています。 ・「考えるのが大変だから解けない」
これは何ができていないのかを自分でも理解できていない子が言います。 この場合はなぜ大変なのかを考えます。 1.考える以前におぼえるものをおぼえていない 2.知識はある程度あるが使い方が分からない 3.考える要素や工程が今の自分のレベルに合っていない 多くの生徒は1,2に該当します。
1,2に該当する生徒は分からないまま進んでいることに気づいていないことが多いので勉強の手順を見直すなどの対処をします。 まれに3に該当する生徒は教材の難易度を落とします。 ・「聞いた方が楽だから分かりません」
これは情報を取りやすい今、google検索などで簡単に調べることによるところが大きいです。 確かに聞くということは勉強する中で大切なことではあります。 しかし自分なりに精一杯考えた過程がなければどこが分からなかったのかが判明せず、いわゆる「分からないことが分からない」状態になってしまいます。 そのため、授業中にこちらから質問をすることで理解度のチェックを定期的に行います。 ・「読むのが大変だから読めません」
このような字を読むことにとても抵抗感を覚える傾向が最近は特に強いと思います。 漫画やゲームなどのストーリーテキストでさえはばかられるほどには顕著です。 読むことに慣れるというのはとても大変なので起死回生の一手のようなものはありません。 なので、文字に触れる、短文を理解するなどハードルの低いところからの挑戦をしてもらいます。
・「問題を解く途中で飽きてしまうので解けません」 この例に関しては身の回りの勉強の環境を今一度確認しましょう。 周りに誘惑するものはないか。 騒音は少ないか。 机の広さは十分にあるか。 適切な明るさでできているか。など 途中で集中力が途切れてしまうことが起きるというのは本人の状態や勉強時間なども関係するので、常に良い環境を作れるようにしましょう。
最後に小学生 早い時期から塾に入ることに関して私の考えを述べたいと思います。
まず、勉強時間の確保ができること。
小学生は特にほとんど自学自習をしなくても受験などは1部にしか関係がなく勉強時間が確保されない子が多いです。
その中で勉強時間を少しでも確保して基礎学習を身につけることができます。
そして、勉強に対してあまり強制力がない時期から始めることで自主性も高まります。
周りの子が塾で勉強しているというエピソードは小学生からすると大人びているように見え、塾に入ってみたいというふうに言われたときには否定せず、試しにやってみるというのも勉強に対して抵抗感が薄まる可能性をあげます。
情報を沢山得やすい現代では小中学生は自分のことを頭が凄くいいと勘違いしてしまうこともあるので、地に足をついて勉強してもらうためにも早めの入塾はとても効果的だと思います。